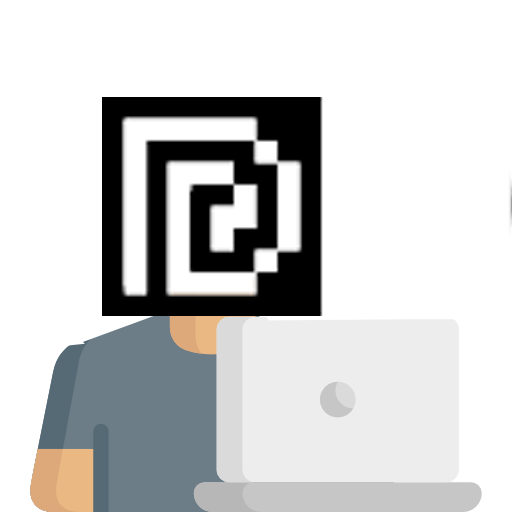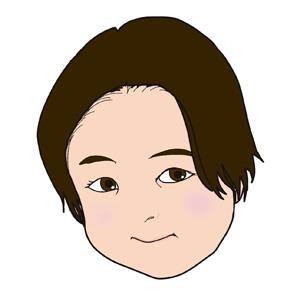2022年9月29日、AnityA・Darsana主催のイベント「生きたデータ活用に欠かせない『組織文化とマインド』を醸成する方法とは フェリシモの山下氏に聞く」が開催された。
本イベントの前半では、フェリシモの山下氏から同社のデータ活用とそのための組織改革や企業カルチャー醸成の取り組みについての紹介が行われたほか、データ総研の伊藤氏からはコンサルタントとして数多くの企業のデータ活用を支援してきた中で培われた「データ活用に必要な組織文化」についての紹介が、そしてJ.フロントリテイリング(JFR)の野村氏からは同社で始まったばかりのデジタル変革の取り組みについて、主に組織やマインドセットの切り口から紹介が行われた。
前半の講演の内容は、別途「データ組織立ち上げに欠かせない『活用のための文化醸成』、どうすればうまくいくのか——フェリシモ、JFR、データ総研に聞く」で紹介しているのでぜひ参照されたい。
後半では、3社の講演を受けて、それぞれの講演者にAnityAの中野仁氏も加えた4人によるパネルディスカッションが行われた。本稿ではその模様をダイジェストでお届けする。
登壇者
・フェリシモ ビジネスプラットフォーム本部 IT推進部 部長 山下直也氏
・J.フロントリテイリング グループデジタル統括部 チーフ・デジタル・デザイナー 野村泰一氏
・データ総研 エグゼクティブシニアコンサルタント 伊藤洋一氏
・AnityA(アニティア) 代表取締役 中野仁氏

イノベーションの火を最初に灯すきっかけは?
AnityA 中野仁氏: お三方の話をうかがって、最も印象に残ったのがやはり「組織文化づくり」の重要性です。この文化を抜きにしてデータ活用の検討を始めても、どうやってデータを活用するか、どんな技術やツールを使うかという“How”(方法論)の話に終始してしまいがちですよね。

データ総研 伊藤洋一氏: そうですね。この文化を醸成するための第一歩は、先ほど講演でも話しましたが「楽しいかどうか」に尽きると思います。やっている自分自身が楽しいと感じて、「自分ごと」として積極的に関われるかどうかが重要ですね。
ただ、いろいろな企業の事例を見ていると、最初にリーダーが口火を切って、「この指とまれ」で興味を持った人が徐々に集まってきても、そこで活動が終わってしまうことも多々あるんです。小さな集団での活動を、口コミでいかに社内に広げていくか。リーダーが最初に誰を仲間にするか。組織文化として広がりを持たせるためには、この点が実はとても重要だと考えています。

AnityA(アニティア)中野氏: こうしたプロセスを経ずに、いきなり「管理」や「実験」からスタートしてしまうケースも多いですよね。組織やルールを定めたり、PoCのプロジェクトをむやみに立ち上げたり、あるいはコンサルタントを外部から入れたりするところから始めてしまう企業も少なくありません。でも、これらは全て“How”(方法論)の話であって、その前にまずは、自分たちが目指すべき“To Be”(ありたい姿)を描いて広く共有しなくてはならないはずです。
フェリシモ 山下直也氏: そのような「信念」がベースとなって取り組みが始まるケースもありますが、一方で「危機感」がベースとなって始まることもありますよね。ちなみに弊社の場合は、後者の危機感ベースの方が多かったです。また、IT部門主導で取り組みを始める場合は、「事業部門部門をはじめとする他部門をいかに巻き込めるか」が重要だと思います。IT部門単独でできることは、どうしても限られてしまいます。
その点、フェリシモはもともと部門間の壁をつくらないようにする企業文化が根付いていたので、やりやすかったですね。弊社では、新入社員や中途採用者の同期同士が月1回集まって、勉強会を開く制度があります。そのため、毎月、必ず他部門の人とコミュニケーションを取る機会があるんですね。そのため、何か全社横断的なことをやろうとした場合、同期のつてを頼ってひょいと組織の壁を越えられるんです。そういった背景から、現在、進めているデータ活用やDXのような全社的な取り組みは遂行しやすい環境だと思います。
J.フロントリテイリング 野村泰一氏: 先ほど伊藤さんがおっしゃった「楽しいかどうか」に付け加えるとしたら、「自分自身の成長があるかどうか」も重要な観点だと思っていて、個人的には結構こだわっているポイントです。やっている本人が新たなスキルを身に付けられたり、一度はあきらめたことができるようになったり、あるいは「今度はできるかもしれない」と思えるようになったりと、自分自身の変化や成長を実感できることも「楽しいかどうか」の大きな要素ではないかなと思いました。
重要なのは、全社でデータを「共通言語化」するための営み
データ総研 伊藤氏: 一方で、データ活用が文化として根付くまでには、信念や危機感以外にも「データの意味や定義」に関する認識が共有されていないと、実際にはなかなか難しいとも感じています。いろいろな企業の例を見ていると、この点で認識がずれていると、文化どころか、その手前の管理のフェーズにすら行き着かないように思います。

JFR 野村氏: そうですね。先ほどの講演でも話しましたが、JFRではマインドセット変革とセットで「プロセス」と「環境」の変革も同時並行で進め、これらを互いに連携させるようにしています。やはり、データ組織のカルチャー醸成とシステム環境・データ環境とは連動すると思います。
どれだけマインドセットを変えようと思っても、環境やプロセスがネックとなってなかなか進まないこともありますし、マインドセットが変わり始めても環境やプロセスの変革が遅々として進まなければ、せっかく巻き込んだ人たちが徐々に脱落していって、最終的に孤立してしまうようなことも起こり得ます。
従って、データ周りの環境の整備やそれを生かすためのプロセス改革は、地道ではありますがしっかりやっておかないと、せっかくマインドセットを醸成できたり人材が育ったりしたとしても、それらをなかなか生かせません。
データ総研 伊藤氏: その点、フェリシモさんでは、普段から部門を越えたコミュニケーションを取ることでデータやプロセスに関する意識合わせを行っているんでしょうか?
フェリシモ 山下氏: そうですね。IT部門と事業部門との間で定期的にコミュニケーションを取る機会を設けています。もう、それこそ「毎週何曜日の何時から何時」と強制的にスケジュールを組んでしまって、最初は各部門のリーダークラスを集めてコミュニケーションを取るように仕向けています。
ちなみにその集まりは、意図的にオープンなスペースで行うようにしています。そうすると、たまたまそばを通りかかった人間が「面白そうな話をしているな」と首を突っ込んできたりして、偶発的なコミュニケーションが発生したりするんですね。特に弊社は先ほどお話したように同期同士のつながりが強いですから、同期が話している場には、気軽に首を突っ込める空気があるんです。

データ総研 伊藤氏: そういう場で、部門ごとの認識を合わせたりするんですね。
フェリシモ 山下氏: それこそ言葉1つの定義や捉え方も、部門によって全く違うことがありますからね。
例えば「引当」という用語も、営業部門では、お客さまから注文をいただいて在庫を割り当てることを引当と呼んでいる一方で、財務部門ではいわゆる「引当金」のことを「引当」と呼んでいることもあります。これはあくまでも一例ですが、このように用語1つをとってみても、きちんと部門間で認識を合わせておかないと、最後のところでふたを開けてみたら「お互いに違うことを言っていた」ということになりかねません。従って、常日頃からの対話を重視するようにしています。
AnityA 中野氏: 言葉の定義を合わせるということは、すなわち考え方や目線を合わせることにほかなりませんからね。
よくデータ活用について話をすると「データカタログをやりたいんです!」という話をいきなりされることもあるんですが、本来はそういう“How”(方法論)の話をする前に、先ほど山下さんがおっしゃったような言葉のすり合わせを最初にやるべきですよね。それを行った結果、「全社共通の辞書として使えるプラットフォームが必要だね」という話になってデータカタログの導入を検討するなら分かるんですが、それを行わずにいきなり「高価なデータカタログ製品」に飛び付いてしまうのは“How”(方法論)がゴールになってしまっているので、うまくいくはずがありません。
部門や個人に課せられた目標値の「その先」にあるもの
AnityA 中野氏: データ基盤やデータカタログの話というのは、一見するとデータやシステムの話をしているようで、実は「自分たちが本来、解決すべき課題は何か?」「何のためにそもそもシステムに投資しようとしていうのか?」という話をしているんですよね。
そして、こうした命題を設定して検討を深めるためには、やはりビジネスやマーケティングの観点がどうしても欠かせません。山下さんも先ほどの講演で、「IT部門もビジネスやマーケティングの観点を持てるように」という話をされていましたよね。

フェリシモ 山下氏: もともと期首に部署や個人の業績目標を立てる際に、私自身もそうなのですがIT部門はどうしても「システムの安定稼働」や「トラブル件数を減らす」といった目標値を掲げることになります。ただし、その目標値を追い求めるあまり、逆にマーケティング部門からの依頼で「事業全体として急いで対応しなければならない案件」を後回しにして、不具合対応の方を優先させるようなことが実際に起きてしまいます。
これは組織設計上、自分たちの目標値がそのように定義されている以上、仕方がない面もあります。でも、弊社はIT企業ではなく、あくまでも事業会社ですから、IT部門に課せられた目標値の「その先にある事業上の目的は何か?」ということを、常日頃から意識する必要があると思うんです。
そうしたことを今一度想起させるために、IT-BSC(バランススコアカード)のような仕組みも導入して、個々の担当者レベルで「自分が受け持っている作業は、事業全体の中で何のためにやっているのか?」ということを書き出して、メンバー同士でレビューし合うようなことを繰り返しながら少しずつ目線を変えていくようなことをしていきました。

JFR 野村氏: 部門横断的に価値をデザインしようと思うと、必ずといっていいほどそういう問題にぶつかりますよね。部門や個人にはMBO(Management by Objectives:目標管理制度)のように必ず特定のコミットメントが課せられていて、一度掲げた目標値を短期間のうちに達成することが求められますから、どうしてもその達成を優先せざるを得ません。
弊社で新たな人材育成の取り組みを始めるときも同様の懸念があったので、あらかじめ人事部門の方に「もともと組織に課せられているミッションを越えた、より大きな利益を追求するための取り組みを進めるということは、人事部門が管理しているコミットメント制度や評価制度と相反することになるかもしれませんが、どう思いますか?」と思い切って聞いてみたんです。すると「今回、私たちがやろうとしていることは、もともとの制度より優先度が上なので構いません」と言っていただいたので、とてもありがたかったですね。
AnityA 中野氏: どの会社も組織体である以上、KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)なりOKR(Objectives and Key Results:目標と成果指標)なり何らかの評価制度は運用せざるを得ないですよね。でも、そこで決められた目標値をひたすら追いかけるあまり、「目の前にある物差しにさえ従っていればいい」という思考に陥ってしまうと、いわゆる「越境」が発生しなくなってしまうんですよね。それぞれの部門が数字を追いかけることだけに目が奪われてしまうと、部門の壁を越えた取り組みに一切、目が行かなくなってしまいます。
その結果、部門間に高い壁ができてしまういわゆる「サイロ化」現象が発生するわけです。成長が止まってしまっている会社の多くは、社内にこうしたサイロ化や官僚主義がはびこって、部門を横断して新たなことを生み出そう、変革を起こそうという気運が全く生まれなくなってしまっているんですよね。
データ組織自体に求められる文化やマインドとは?
AnityA 中野氏: 参加者の方々から登壇者に対して質問が寄せられているので、その中から幾つかピックアップするので、お答えいただければと思います。
1つめの質問は、「お話しされている組織文化とマインドは、今、多くの部門に求められているもののようにも理解できます。『データ活用』に特化した、あるいは他部門と比して強く求められる『組織文化とマインド』はあるのでしょうか?」というものです。

JFR 野村氏: 他部門と比較してデータ活用についてよく言っているのは、「データの流れを見ることによってステークホルダーを増やすこと」ですね。データの流れを子細に追っていくと、業務の流れだけではなくて、「データに関わるさまざまな立場の人たちのつながり」が見えて来るんですね。データを生かしてくれる人もいれば、全く生かしていない人、あるいはデータの流れを止めてしまっている人などさまざまな人が見えてきます。
そうした分析を基に「ステークホルダーマップ」のようなものを作りながら、データをデータとして見るだけではなく「データの価値を拾えるマップ」として見るように心掛けていると、後々になって困ったことが出てきたり「あともうちょっと何かが足りないな」「ここを何とか突破できれば」と思った時に、味方になる人を見つけやすくなるんです。
フェリシモ 山下氏: 弊社では、先ほどから繰り返し述べているように「危機感を自分ごととして」とらえてもらえるよう、社員に働きかけているのですが、その一方で「自分ごと化」しすぎてデータに対するオーナーシップを過度に意識するのも、データの「囲い込み」「サイロ化」を招きかねないためかえってよくないとも考えています。
データはあくまでも「誰のものでもない共有材」であって、「皆でうまく使っていこう」という文化を根付かせるためには、「自分ごとだから、全部自分たちでやろう」ということにならないよう、うまくそのへんをぼかす工夫も意識しています。
データ総研 伊藤氏: 私がかかわっている企業の成功例を振り返ると、やはり最初の段階では小さくスタートさせて、少人数のラボのような活動で少しずつ成功体験を作っていきながら、徐々に他部門を巻き込んでいっていますね。
他部門を巻き込みながら仲間を増やしていくに当たって、よくありがちなのが、デジタル活用やデータ活用に関する社内教育制度を実施するやり方なのですが、これだけでは、ほぼ確実に失敗していますね。そうではなく、現場でOJT的に生きた事例を用いたPBL(プログラムベースラーニング)のような形をとると、うまく他部門を巻き込めるケースが多いです。
AnityA 中野氏: 次に「野村さんは外部から入って、組織風土作りまでを手がけているようにお見受けするのですが、抵抗が強い部署などを相手にしていると心が折れたりしないんですか? そのあたりのマインドセットをお聞きしたいです」という質問をいただいています。
JFR 野村氏: 組織風土まで手を入れないと変革は実現できませんから、そこは逃げずにやっているというところです。ただ、社内の抵抗が強いかどうかという点については、私自身がそうした点について鈍感なのであまり感じていないのかもしれません。仮にそうした人たちがいたとしても、彼らを最初に説き伏せようとするより、まずは興味を示して向こうから集まってきてくれた人たちを味方につけながら小さく始めるようにしています。
それと同時に、取り組みの内容を社内に広く告知することで、むしろ抵抗勢力をマイノリティのように見せたり、社長の同意を取り付けて折に触れて「これ、社長がこんなこと言ってたんですよ」と冗談交じりに話すことで、何となく経営トップのコミットを匂わせるようちょっとした工夫もしていますね。
AnityA 中野氏: 確かに、抵抗勢力になることが初めから分かっているところにいきなり突撃するより、興味を持って集まってくれた人たちと組んだ方が成果も出やすいし、成果が出れば結果的に外堀も埋めていけますからね。あとは経営トップのコミットメントも得られれば、もちろん説得力はより増しますよね。
野村さんは当たり前のように話していますけど、JFRのような老舗の大企業で、転職してきたばかりの人がそうした社内政治力を発揮するのは、普通、なかなかできることではないと思います。
生きたデータ活用に欠かせない「組織文化とマインド」を醸成する方法とは フェリシモの山下氏に聞く