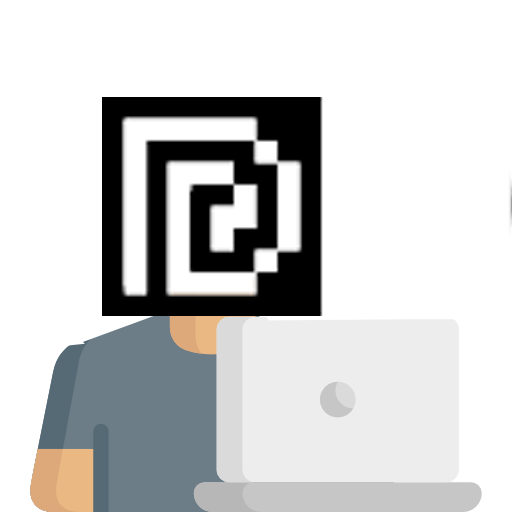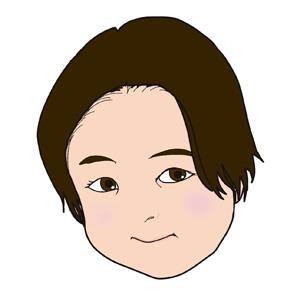データ活用を成功させるためには、部門横断のデータ組織を作ること——。部門間の分断とそれに伴うデータの分散が「本質的なデータ活用を阻む」という反省から、こうした方針のもとでデータ組織を立ち上げる企業が増えている。
しかし昨今、「データ組織を立ち上げたものの、うまく機能しない」と悩む声が挙がっている。データ組織がうまく機能しない理由は企業によってさまざまだが、その要因として「データ組織の文化」を醸成できていない点や「データ活用のカルチャー」が根付いてない点などが挙げられる。
9月29日にAnityA(アニティア)とDarsanaが開催した「データ組織を機能させるための要素について考えるイベント」では、実際に社内でデータ組織の文化づくりに奔走した結果、全社的なデータ活用の推進に成功したフェリシモの事例を紹介。合わせて、データ活用のための文化の醸成をベースにクライアント企業のデータマネジメントを支援するデータ総研の知見を紹介するとともに、J.フロントリテイリング(JFR)が始めたばかりのデータ活用とDX施策の概要も紹介した。
本記事では、それぞれの講演の模様をお伝えする。
データ活用の文化を根付かせるためのポイントは「楽しいかどうか」
イベントの冒頭に登壇したデータ総研 エグゼクティブシニアコンサルタントの伊藤洋一氏は、「データ組織と文化の相関関係 データ活用を成功に導くための組織文化づくり」と題した講演で、これまで同氏がさまざまな企業のデータマネジメントの取り組みを支援する中で培ってきた、「データ組織の文化づくり」に関する知見を紹介した。

伊藤氏は現在、データ総研でデータガバナンスやデータマネジメントの組織づくり、人材育成支援、データ基盤の構築支援などに携わっているが、近年は「教育学」の観点から組織文化づくりにアプローチすることが多いという。その際には、例えば「共通言語」「場」「循環(サイクロン)」「認知徒弟制、正統的周辺参加」といった教育学その他のコミュニティ理論を応用しているという。
数ある組織の中でも、特に「データ組織」に注目した場合、企業や業種によってデータに興味を持つきっかけはさまざまであるが、どの企業にも共通して見られる傾向として、データ活用に関して「3つの不安」を抱えていると伊藤氏は指摘する。具体的にはデータの品質管理がしっかりなされているという「安心」、データがきちんと構造化・整流化されているという「安定」、そしてデータがしっかり保護されているという「安全」の3点が担保されていないという不安だ。
これらの不安を解消するためには、メタデータの整備による「安心」の獲得、データモデリングによるデータの「安定性」の確保、そしてデータセキュリティの確立による「安全性」の確立が必要となる。そして組織体制としては、データガバナンス組織を頂点として、その下にデータ運用支援組織、データ活用支援組織などが配置される体制を確立するのが理想だが、これらの組織づくりのやり方や手順、タイミングを間違うと「絵に描いた餅」に終わってしまうと伊藤氏は指摘する。
「こうした組織体制を確立するのが理想的ですが、初めからいきなり組織の器だけをつくっても、社内でデータ活用の気運は一向に高まらず、すぐに形骸化してしまいます。そうではなく、社内でデータ活用の気運が高まって、いわば『火のついた状態』になってから組織の器をつくることをおすすめします」(伊藤氏)

では、そもそも組織内で新たな文化を根付かせるには何がポイントになるのか。同氏は真っ先に「楽しいかどうか」を挙げる。楽しそうなところに人は自然と集まり、その活動が徐々に広がっていき、最終的に文化として根付く。そしてデータ活用の「仮説構築」「データ収集」「仮説検証」「意思決定」の各工程の中でも、最も楽しいのは「仮説構築」だと話す。
さまざまなビジネス目的を挙げ、それぞれを達成するために使えるかもしれないデータを抽出し、それらの活用がビジネスになりうるかどうか相関を調べてシミュレーションを行う——という取り組みが、データ活用の工程の中でも最も楽しく、多くの人が自然と集まり、組織の「火が付く」場でもある。
そして最初に火を灯し、多くの人々を巻き込んでいきながら、最終的に組織文化にまで広げていくためには、やはりその取り組みをリードする強力なリーダーの存在が不可欠だ。リーダーが始めた活動に対して、「この指とまれ」で多くの人が共感して集まり、その活動が口コミで徐々に社内に広がり、やがて正式な組織が立ち上がり、最終的には企業カルチャーとして定着する、というわけだ。

「こうした組織づくりのメカニズムが機能するためには、その中心となるリーダーがビジネスに役立つ仮説立てができ、臨場感をもって取り組みをリードしていく必要があります。その際には、やはり仮説構築のフェーズに着目した方が火はつけやすいでしょう。また、仮説構築で利用したいデータの『定義』について、皆で考えることも知的好奇心がくすぐられるため、自然と多くの部門の人たちが集まってきます」(伊藤氏)

DWH基盤のリプレースに合わせて組織運営とスキルセットも再定義
続いて登壇したフェリシモ ビジネスプラットフォーム本部 IT推進部 部長 山下直也氏は、「データ活用を推進するアプローチ」と題した講演で、フェリシモが現在、進めているデータ活用の取り組みと、そのために行った組織改革、人材育成、スキル・マインド醸成の施策を紹介した。

神戸市に本拠を構えるフェリシモは、1965年創立の老舗通販企業。主に女性向けのファッション、生活雑貨、手づくりキットなどの通販事業で知られ、もともとの主力チャネルであったカタログ通販に加え、近年ではECサイト経由での注文も急増している。また一度きりの商品買い切りだけでなく、毎月1回色柄デザイン違いの商品を届ける「頒布会方式」のビジネスモデルを主力とする。
そんな同社では、2010年ごろ業績の伸びに鈍化が見られ始めたため、新たな施策を講じる必要性に迫られた。その中心となる施策がデータ活用だったという。
「それまでのカタログを中心としたビジネスモデルから、多様なチャネルを通じてお客さまについての理解や洞察を深めて、幅広い関係性を築いていく必要があると考えました。そのためには顧客データを集計・分析するマーケティング分析基盤が不可欠ですが、それまでの分析基盤は商品軸で設計されており、顧客軸での分析には向いていませんでした」(山下氏)

同社では分析基盤を実装していたデータウェアハウス(DWH)も老朽化が進み、リプレイスの必要性に迫られていた。加えて、IT部門とデータ分析部門、事業部門の連携がうまく取れておらず、組織運営やスキルセットの見直しも必要だった。そこでDWHのリプレイスを機に、IT部門とデータ分析部門が共同でプロジェクトを組み、新たなデータ分析基盤を構築するとともに、組織運営とスキルセットの再定義も合わせて行っていくことになった。

なお、既存の分析基盤はオンプレミス環境上で運用されており、容量の拡張性に制限があるほか、基幹システム以外のシステムとのデータ連携が不足していた。そこで新分析基盤はスケーラビリティに優れたクラウド基盤上に構築し、基幹システム以外のデータもDWHで集中管理することにした。
また、基幹システム以外のデータを使った分析を行う際には、DWHを介さずにデータソースから直接データを抽出しており、データ抽出のためのインタフェース開発にも多くの工数が掛かっていた。そのためリプレース後はETLツールを導入してインタフェース開発を標準化・内製化することとした。
さらにはデータの加工・変換もさまざまなレイヤーで行われており、データ活用のスピード低下やデータ品質低下の原因となっていた。そこでこの課題を解決するために、データの加工・変換処理は中央で集中的に実行する構成とした。各種レポートの作成作業に関しても標準化し、中央で一元的に実施することで品質向上を図った。
ほかにも、社内にどのようなデータが存在し、どのように活用されているのか横断的に理解している人材がいないため、データを有効活用するための戦略策定が進まないという問題もあった。そのためDWHリプレースと合わせて、自社全体のデータ理解を促進するための「データマップ」「データカタログ」も整備することにした。
「まずはDWHのクラウド化、次にインタフェース開発の標準化・内製化、続いてデータ加工・変換処理の整理、BIツール導入と合わせたレポートの定型化、そして最後にデータマップやデータカタログを整備してデータ理解を強化するというロードマップに従ってDWHをリプレースすることになりました」(山下氏)
自ら「提案」「発信」「越境」していけるマインドやスキルを育む
組織面においては、IT部門とデータ分析チーム、IT部門間の非効率なコミュニケーションパスを改善するために、これらの部門を横断する組織として「データ基盤チーム」を新設。既存の各システムのチームから兼任でメンバーを集め、サイロ化していた各システム間のデータ連携やデータハブに関する管理・運用を行うようにした。


この新組織は、データ活用に関するOJTを行う組織としても機能し、各システムチームから若手メンバーを集め、データ基盤チームで一定期間OJTを実施することで社内データに関する理解を深めてもらった後に、再びシステムチームに戻り、それぞれの領域でデータ活用を進めてもらう。
具体的な活動内容としては、週に1回の頻度でIT部門や分析チーム、事業部門の関係者を一同に集めて事業課題の抽出やマーケティング施策の立案などを検討したり、データ出力の仕様やBIツールのダッシュボード設計などを行う。ここで全体の方針が決まった後、実際にデータ基盤チームのメンバーが中心となり、データの収集・加工・蓄積を行う。
これら一連のプロセスをウォーターフォール型の受託開発ではなく、IT部門側から積極的に提案し、短期間で仮説検証を繰り替えるアジャイル型のプロセスを内製で繰り返すやり方を採用した。


こうした組織改革と並行して、マインドやスキルを磨くための人材育成施策にも取り組んだ。その際に最も重視したのは、課題や危機感を「自分ごと化」させることだと山下氏は語る。
「『2025年の崖』などで提示されている課題やリスクは弊社の状況にもそのまま当てはまるのですが、これを他人事として傍観するのではなく、まずは『自分ごと』として捉えて危機感を持ってもらうことが、マインドセット変革において最も重要なポイントだと思います。ただし、社内に閉じこもっていると、こうした危機感を肌で感じにくいので、社外や市場の状況に積極的に目を向けて、自分たちの立ち位置を常に客観的に評価する姿勢が重要だと思っています」(山下氏)
改革の機運を高めてマインドセットを変えていくために、これまで事業部門が決めた戦略に則ったシステム開発に専念していたIT部門の役割を拡大し、IT部門が自ら戦略を策定したり、戦略を実行した後の評価に積極的にかかわるようにした。データ活用人材に関しても、従来の「SoR人材」「SoE人材」に加えて、SoR領域とSoE領域を行き来できる「SoI(System of Insight)人材」の育成に力を入れている。
さらにはIT部門のメンバーが視座を高く持って事業やマーケティングの観点から事業部門とデータ活用に関してコミュニケーションできるよう、チームや個人の評価指標に「提案」「発信」「越境」などの要素を盛り込んで、「事業に貢献できるデータ活用」を推進するマインドづくりに取り組んでいる。


データ活用に関するスキル強化にも力を入れており、ITとビジネスの双方の立場からデータ活用の教育を行って、データを「抽象化」できるスキルを高めながら、事業全体のデータに関する理解を深められるようにしている。またIT-BCS(バランススコアカード)を導入し、自分たちの活動が事業活動のどの部分と紐づいているかを意識できるような工夫も凝らしているという。
ほかにも、自社におけるデータの配置や流れを全社レベルで把握できるようデータの俯瞰図を作成したり、同業種をモデルにしたモデリングのワークショップを開催するなど、データ活用スキルを多面的に高められる施策を講じている。

「今後はDMBOK2(データマネジメント知識体系ガイド 第二版)のフレームワークを意識しながら、データをよびビジネスに引き寄せるための活動を強化していきたいと考えています。そのために、既存人材のリスキリングを進めながらデータ活用人材の育成にさらに力を入れていく予定です」(山下氏)
国内屈指の歴史を持つ老舗企業でDXを推進するためのポイントは?
続いてJ.フロントリテイリング(JFR) グループデジタル統括部 チーフ・デジタル・デザイナーの野村泰一氏が登壇し、「変革に向けたマインドセット醸成のポイント」と題した講演で、現在、同社がDX推進の柱の1つとして進める「マインドセット醸成」の取り組みについて紹介した。

野村氏はもともと全日本空輸(ANA)におけるDXの推進役として数々の成果を上げた後、2022年4月にJFRに入社。同社のDX推進をミッションとして、さまざまな改革を進めている。そのためには、まずは何より変革を志向するマインドセットを社内に根付かせることが先決だと考え、DXの変革マインドを「JFR花伝書」と名付けたドキュメントにまとめた。

ただし、単にマインドセット変革のための絵を描いて示すだけでは、実効性のある取り組みには結びつかないと野村氏は語る。
「実際には社内のさまざまな既存プロセスが変革の壁となって立ちはだかったり、口では『変えていこう!』と唱えながらいざ他人が変革に乗り出すと途端に抵抗勢力に転じる人もいます。ただマインドだけを変えても、プロセスや環境が旧態依然としているとかえってフラストレーションをためる結果になってしまいます」(野村氏)

そのためマインドとプロセス、環境をしっかり連動させることが重要になってくる。その上で、DXをリードしていけるデジタル人材を育成するための施策を同時に実施していく、というわけだ。
ただし、人材育成の前にまずはその前提となるデジタル戦略をしっかり策定し、その実現に必要な人材を定義した上で、新たなビジネスを起こしていくビジネス人材と、データ活用を推進する人材の両方を育成していく。そして環境やプロセスをつくりながら人を育成し、その過程でその人の中にマインドをしっかり根付かせていくという方針で現在さまざまな育成施策を進めているという。
例えば、実際のビジネスの現場で起こり得るリアルなシナリオをいくつか設定し、そこで持ち上がる課題を解くために前出の花伝書のどの部分を適用すればいいかを確認しながら、ロールプレイイング方式でデジタルによる課題解決が学べる研修を実施している。同じく、ビジネス課題をデジタル技術で解決する手段を、ステークホルダーが一同に集まって検討するワークショップも実施している。
なお、IT部門では、社内でより多くの社員がデータを活用できるよう、データ基盤とツールの整備と提供を担うが、単にツールを現場に提供して終わりではなく、IT部門が自ら現場のビジネス課題の解決にコミットするようにした。IT部門が率先してこうした姿勢を示していくことで自ずと変革のマインドセットが醸成され、現場との関係性も変わってくるという。
また人材育成の教育プログラムの修了者は、プログラム終了後は業務部門に帰って行くことになるが、せっかくマインドが醸成されても、部門に戻ると途端にビジネスの現実に直面し、マインドが萎えてしまうことも少なくない。そのため、修了者同士がバーチャルなコミュニケーションを形成してDXのマインドセットを共有できる「バーチャルCoE」と呼ばれる仕組みも設けた。

そのほかにも、育成施策の検討・実施に当たっては人事部門とも密接に連携し、どこよりもまず人事部門に真っ先にプログラムを体験してもらうことで人事部門の当事者意識を喚起してもらう工夫も凝らしている。
「JFRは大丸や松坂屋など非常に歴史の古い企業が母体になっていますから、外から見ると保守的なイメージがありますが、実際には私のような人間が新しいものを持ち込んでも、決して入口で否定されるようなことはありません。まだDXの取り組みは始まったばかりですが、データ活用やDXの文化を根付かせるためにはただ単にマインド変革を叫ぶだけでなく、日ごろのプロセスや仕組みの中にマインドをいかに練り込んでいくがポイントになると思います」(野村氏)
生きたデータ活用に欠かせない「組織文化とマインド」を醸成する方法とは フェリシモの山下氏に聞く