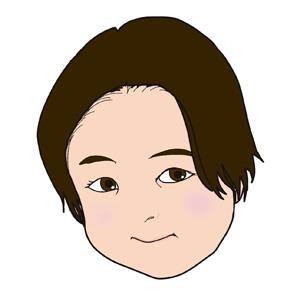「我々に求められるのは、アフター・コロナをただ待つのではなく、ウイズ・コロナを前提とした変革への覚悟です」──。
自社サイトのトップメッセージで、こう危機感をあらわにするのは、J.フロントリテイリング(以下、JFR)の代表取締役社長を務める好本達也氏だ。
JFRは、2007年に百貨店の大丸と松坂屋が経営統合した際に設立された共同持株会社で、ショッピングセンターのパルコも傘下に持つ。コロナ危機からの完全復活と再成長を目指している同社は、2021年度から新たな中期経営計画をスタートさせている。
そんな同社は今年度を、コロナ危機への対応という「守り重視」から、トップラインの成長を追求する「攻め」に転じる年と位置付けており、人材育成にも積極的に投資する計画だ。
こうした中でこの春、同社にある人物が入社したことがわかり、DX界隈の人たちを驚かせた。全日本空輸(以下、ANA)でデータ活用を中心としたDX施策を牽引してきた野村泰一氏がJFRに転職し、グループデジタル統括部のチーフ・デジタル・デザイナーに就任したのだ。
野村氏は、従来の取り組みの延長線上にある「改善」ではなく、新たな視点でビジネスの成長を考え、場合によってはこれまでのやり方を変えることも辞さない「改革」を企業に根付かせることを目指して、DXを推進してきた変革の第一人者だ。
変革を実現するためには、「スキルやツールだけに頼るのではなく、部門を横断して課題解決に取り組むためのマインドセットを醸成することが重要」──というのが、野村氏の考え。新たな改革のフィールドとなったJFRでも、さっそくJFRに必要なマインドを醸成するための取り組みや、人材育成、システム活用のための施策を仕込んでいるという。
「社外のDX担当の方々と話をする中で、これまでANAで手掛けてきた一連の取り組みが、もしかしたらほかの業界にも通用するのではないか、と思うようになったんです。そんな中、経営トップが大きな危機感を持って改革を断行する覚悟を決め、DX推進というフィールドを私に与えてくれたのがJFRでした。4月に入社して4カ月ですが、いよいよこの秋からデータ活用のための仕組みづくりと人材育成を本格化させます」(野村氏)
野村氏は、江戸時代から続く老舗百貨店の大丸、松坂屋と、若者文化の発信拠点PARCOを擁するJFRをどこからどのように変えていこうとしているのか──。秋から本格的な改革の第一歩を踏み出す同社の取り組みについて、野村氏に聞いた。

ANAからPeach Aviationに移籍、再度ANAに戻った経験がDX推進の糧に
──(聞き手:後藤祥子) 野村さんは、長年務めたANAを退職して、航空ベンチャー、Peach Aviationの立ち上げに参画し、その後、ANAに戻ってデータ活用を中心としたDXを推進してきました。自身のDXスタイルを確立するのに、これまでの一連の経験はどのような形で役立ちましたか?
野村泰一氏(以下、野村氏): 大企業(ANA)とベンチャー(Peach Aviation)、システム部門とオペレーション部門、営業部門など、異なる社風、異なる役割を幅広く経験したことが、DXを推進する上で大きな糧になりました。
若い頃に、ANAでレガシーなシステムを使ったビジネスモデルの開発を担当しており、メインフレームやWeb、端末まで一通り触っていたことが、とても役に立っています。こうしたスキルを身につけた上で、航空ベンチャーの立ち上げを経験し、さまざまなビジネスを一からデザインできたのは、自分の強みになっていると思います。
これまで手がけてきたDXのデザインは、データプラットフォームをベースとしたBtoCのモデルづくりやデジタルテクノロジーを使ったビジネスデザイン、それを生み出すための組織設計やマインドセットの浸透、人材育成──といった要素を「合わせて実行する」というスタイルで、これが私の流儀であり、ポイントだと思っています。
この4月からはJFRで、これまでの経験を生かしながら「JFRならではのDX」をデザインし、実装していく計画です。
なぜ、多くの企業で「改革プロジェクト」がうまくいかないのか
── 「改革」を起こそうとしているのに「改善」にとどまってしまう、「コストを投入し、努力もしているのにDXが思うように進まない」と悩んでいる企業が少なくありません。ANA時代に「部門を超えて協力しよう」という文化を醸成し、挑戦を恐れないマインドを浸透させた結果、さまざまな改革を成功させた経験から、企業が「改善」にとどまらない「改革」を起こすためには何が必要だとお考えですか?

野村氏: たしかに、「改革のための努力や投資が、一向に結果に結びつかない」という話はよく耳にします。
そういう方々に、どんな取り組みをしているのかとお聞きすると、「現状の取り組みに対してPDCAを回して改善しています」「新たにデータプラットフォームを導入しました」「データ活用のためのデータサイエンティストを雇用したり、社内人材をデータサイエンティストにするための育成を行いました」──といったことを実行している企業が多いようです。
もちろん、こうした取り組みは重要なのですが、これまでと同じ組織構造の中、同じマインドのもとで取り組んだのでは、「従来の延長線上の取り組みにとどまってしまう」と思うのです。それは「改善」であり、なかなか「ダイナミックな改革」には至りません。
どういうことかというと、「改善」は「既存のモデルが磨かれるもの」であり、現状からの脱却、つまり、これまでにない大きな成果や新たなビジネスモデルの獲得にはなかなかつながりません。
一方の「改革」は、「これまでの方法論やビジネスモデル、組織のあり方を否定することすらあるほどの、大きな変化を起こす取り組み」なので、反発や抵抗などの摩擦は必至です。それでもなお、覚悟を決めて取り組むからこそ、大きな成果や新たなビジネスモデルを生み出すことができるわけです。
DXはまさに「改革」ですから、従来の組織構造やマインドセットの上で「仕組みづくり」と「人材育成」を行うだけでは、なかなか変化は起こせません。企業のありたい姿から逆算し、それを実現するために必要な「マインドセットの醸成」と「それを根付かせるためのプロセスづくり」もセットで行わないと、せっかくの仕組みやスキルが生かせないままになってしまいます。
前職の取り組みにおいても、デジタル化のための仕組みづくりをしただけではありません。仕組みを生かすためにはマインドセットが大切ですから、まずはイノベーションを担当する部門からその意識を変え、ワークショップや案件構築をきっかけにコミュニケーションすることで、他の部署にも伝播するよう心掛けました。
例えば「失敗しても責めず、そこからの学びを今後の取り組みに生かそう」というマインドは、納期と品質を絶対視する風土を持つ部門にとってはとても大きな変革です。しかし、こういうマインドへのこだわりが、人財育成に影響し、さまざまな改革施策につながったという実感があります。
つまり、さまざまな施策を「改革」につなげるためには、
・システム環境と人材育成、業務プロセスといった「変革要素」の連動
・マインドセット、スキル、ナレッジを掛け合わせた人材育成
・組織機能とデジタル人材の一体化
といった取り組みが欠かせないと考えています。JFRでは、こうした考え方に基づいた変革を進めていこうとしています。
各地の百貨店、ショッピングセンターに足を運んで見えてきたこと
── 4月からJFRに転職し、この秋から本格的な改革をスタートさせようとしています。百貨店やショッピングセンターの課題を知り、改革のロードマップを描くために、まず、何から始めたのでしょう?
野村氏: 入社して最初の1カ月は、百貨店とショッピングセンターを理解するために、JFRの店舗を観察したり、現場で働かせてもらったり、(コロナ下におけるルールの範囲内で)現場の人と飲みに行ったり──ということをしていました。
全く異なる業界からの転職だったので、最初は店舗に行っても「どこをどのように観察したらいいのか」が全然わかりませんでした。空港なら、「ここはこういうコンセプトだから、こういうデザインになっているんだ」と、すぐわかるのですが(笑)。
ですから最初のうちは、同行してくれた店舗スタッフに「どんなことを考えてこのような店構えにしているのか」「このフロアはどんなお客さまをターゲットに、どのような考えで設計しているのか」──といったことを、ひたすら聞いていました。
これは、本当にいい勉強になりました。「店舗のみなさんは、こういうことを考えながら働いているんだ」「このような考えのもとでサービスや売り場を設計しているんだ」──ということが次第にわかってくるのは、とても興味深い体験でした。「なるほど、こういう考え方をすれば、良いデザインが生まれるのか」ということも見えてきたんです。
── 店舗を回ったり、現場や社内の人と話す中で見えてきたことは?
野村氏: 入社するまでは知らなかったのですが、大丸も松坂屋も、とても歴史がある会社なんです。大丸の創業は1717年で、暴れん坊将軍(徳川幕府8代将軍 徳川吉宗)の時代。松坂屋は前身である呉服屋を創業したのが1611年で、これは徳川家康の時代です。パルコも新しい会社と思われがちですが、実は設立は1953年で、テレビ放送が始まった年なんです。
これだけ歴史がある会社だと、新しい人が入ってきた時のお作法がいろいろとありそうな気がするじゃないですか。それが実際に入ってみると、そんなことはなく、新しいことを受け入れる土壌があったんです。
JFRに入って4カ月経ちますが、外の視点で見えたことを伝えたり、新しい取り組みを提案した時に、頭から否定されたことは一度もありません。こうした、「入り口で否定せず、新しいことを受け入れる文化」があるからこそ、何百年も生き残ってきたんだ、と実感しました。
ただ一方で、「現状から大きく抜け出せていない」と感じたのも事実です。店舗を回ると、現場のみなさんは、厳しいと言われる状況の中でも、「お客さまとの関係をどう築いていけばいいのか」「百貨店、ショッピングセンターとしてのポジションをどうやって上げていくのか」ということにとても尽力しています。しかし、「現状をベースに、より良くしていこう」という活動が中心になっているという印象を受けました。

── 外の視点で見たからこそ、気づいたことはありましたか?
野村氏: 大丸、松坂屋、パルコともに、それぞれ長い年月をかけてつくってきた歴史や文化があるので、どうしても「個別の店舗」「個々の百貨店、ショッピングセンター単位」でがんばる──という考え方から抜け出せていない印象を受けました。
もちろん、これまでこのような形で組織をつくり、ミッションを渡してきたので当然だと思いますが、それぞれの文化を大事にしながら横の連携をつくることができたら、面白い化学反応が起こると思ったのです。
そこで今、2つのことをテーマにしています。
1つは、「大丸、松坂屋、パルコのデータを掛け合わせることで生まれる“新たな価値”を探ろう」ということです。
例えば、近接したJFRの店舗が共同でキャンペーンを展開した場合、店舗スタッフの中には、「うちのお客さまが、向こうの店舗に取られているんじゃないか」と思う人もいるかもしれません。その時に、データ分析で「単体の店舗だけで買い物する人よりも、両方の店舗で買い物をする人の方が購買金額が多い」という結果が出たとしたらどうでしょう。実はこれは、実際にそうだった、というデータの裏付けがあるからまた、面白いお話なのですが。
店舗同士で協力した方が売り上げが伸びる、ということになれば、店舗スタッフは「両店舗で買い物をしている人の特徴」や「買っているものの傾向」「立ち寄る店の傾向」などといったデータを知りたいと思うようになるはずです。こうした「店舗をはしごするお客さまの傾向」が見えてくれば、共同キャンペーンもより立体的なものになるはずだし、施策に「お客さま視点の深み」がでてくると思うのです。
このような、「単に売り上げを上げるためだけではないお客さまとの関係」を、店舗横断でデータを使って育てていこう、というのは大きな目標の1つです。
もう1つは、「若者、ミドル、シニアという“幅広い世代をカバーする百貨店とショッピングセンターを持っていることの価値”を生かそう」ということです。
パルコの顧客は若い世代が中心で、大丸、松坂屋はミドルやシニア世代が中心です。パルコのお客さまは、大人になって大丸や松坂屋のお客さまになるかもしれないし、大丸、松坂屋のお客さまのお子さんやお孫さんは、成長するとパルコのお客さまになるかもしれない。
ここをうまくつなぐことで、他の百貨店にはない価値を出せると思うのです。私たちはこのつながりを、「カスタマージャーニー」と「ライフタイムバリュー」を掛け合わせた造語で「ライフタイムジャーニー」と呼んでいて、「世代をまたぐブランドを持っていること」を意識してビジネスをつくっていこうじゃないか、という考えを発信し始めています。
この意識が浸透すれば、大丸、松坂屋、パルコのスタッフが、それぞれの顧客を紹介しあったり、互いの持つデータを生かしたり──という動きにつながるはずです。
このように、JFRグループが持つ強みを、面的に、そして時系列的に生かすアプローチを、データ活用でサポートしたいと思っています。
マインド、スキル、ナレッジを浸透させるための人材育成法とは
── JFRの現状を知った上で、どこからどのような形で改革をスタートさせようと考えていますか?
野村氏: 大丸、松坂屋、パルコのデータを横断的に活用するためのプラットフォームを導入したり、データサイエンティストを育成したり──ということは、もちろん考えていますが、それを生かすための土壌(マインドセット)と、土壌を育むためのプロセスがないと、改革が進まないというのは、先にお話しした通りです。
こうした話を社内のいろいろな方々とする中で、「JFRに変革を起こすためのマインドセット」と「ナレッジ」、「スキル」を掛け合わせて変革人材を育成していきましょう──と提案したところ、各社の人事の方々からそれを後押しする賛同の言葉が挙がってきたのがうれしかったですね。「これは話がはやい」と思いました。
こうした取り組みを通じて、人の役割と組織の機能を一体化させ、連動させることができれば、大丸や松坂屋、パルコがもともと持っている価値がさらに生きてきて、改革の歯車が回り出すはずです。

── マインドセット×ナレッジ×スキルとシステムが連携することで、どのような効果が生まれるのでしょうか。
野村氏: 例えば、データレイクがあったとして、それを既存のプロセスで使っていくだけだと、利用範囲が限定的になってしまったり、現行での活用が磨かれるだけにとどまったりしてしまいがちです。
しかし、これを「データ活用のスキル」を持ち、なおかつ「現場の業務や課題を理解している人」が使い始めると、データを使った「より深い洞察」が得られるようになり、新たな価値が見えてきます。そうすると、「このデータレイクに、もっとこういう情報があればいいのに」といった気づきも自然と生まれます。
その結果、「データレイクを使いながらビジネスで成果を上げ、その価値をもっと生かすためにデータレイクを育てる」──というサイクルが生まれるようになります。これがシステムと人材とプロセスが連携した一つの形です。JFRはデータレイクを持っているのですが、現状はこのような活用ができていないので、活用のための仕組みをつくっていこうとしています。
── 組織横断でJFRが抱える本質的な課題を解決するために、どのような形で人材を育成していこうとお考えですか。
野村: JFRのデジタル人材育成では、「マインド」「スキル」「ナレッジ」の教育を行う計画です。この3つをベースに、組織の機能と連動した「データアナリスト」「デジタルデザイナー」という2タイプのデジタル人材を育成しようと考えています。
データアナリストは、分析のスキルはもちろんですが、ビジネス視点を持ってもらうことを重視しています。分析したデータをもとにビジネスデザイナーと「どうでした? だったらここはもっとこうしましょうか?」とコミュニケーションすることで、ビジネスデザイナーの洞察を深める支援ができる人材を育てようとしています。
デジタルデザイナーは、ビジネスとテクノロジーの知識を背景に、組織の課題解決やミッションを実行する方法をデザインする役割を担っています。ここで重視しているのは横断的な目線です。これから大丸、松坂屋、パルコの価値を掛け合わせて生まれる新たな価値をつくっていくので、この視点は欠かせません。JFR全体としての価値を出しながら、個々の売り上げにも貢献できるようなデザインができるといいですよね。
この2つの機能が改革のエンジンになり、相互に連携することで、分析したデータの価値が高まり、デザインがより良いものになっていくはずです。

いずれの人材にも共通する教育プログラムとして用意したのが「JFR花伝書」と銘打ったJFRのマインドセットを醸成するための教科書です。ANA時代につくったプログラムは、宮本武蔵の兵法書に例えた「五輪書」でしたが、JFR向けには「歴史ある会社」ということから室町時代末期に世阿弥がまとめた能楽伝書「花伝書」を使うことにしました。
これは、「JFRの改革を推進するためのベースとなる行動規範」という位置付けで、JFRの社長を務める好本が社内に呼びかけている「失敗を恐れず挑戦しよう」「自分で考えて行動しよう」いう行動指針(JFR-Way)が実践できていない、という思いを受け止めたものになっています。
例えば、ここに記されているDXの心得に沿った行動ができなければ、たとえどれだけ優秀なデータサイエンティストでも評価されることはありません。マインド、スキル、ナレッジが三位一体となって身について初めて、JFRを変えていく人財になれる──というわけです。

── JFR花伝書のポイントとなったのはどの部分ですか。
野村氏: 一つは、最初に「スピード」の話を持ってきたところですね。歴史ある会社がスピードを意識するようになれば、大きな変化を起こせると思ったのです。
もう一つは「花の本質を知ろう」というところ。これは、「人は自分自身を成長させ、自らの気持ちを研ぎすましてこそ、美しく咲くことができる」ということを伝えるものです。
どういうことかというと、お客さまに接する仕事をしている人は、「お客さまを大事に思うあまりに、自分を犠牲にすることがあたりまえのような感覚」になっている場合があるからです。JFRにも、少なからずこの傾向がありました。
例えば百貨店は、お客さまがお買い物をするエリアはとても居心地良くつくられていますが、一歩裏に入って事務所スペースを見ると、とても古いつくりのままだったりするわけです。もちろん、これは悪いことではありませんが、「自分自身を大事にしてこそ、もっともっとお客さまを大切にできる」──という考え方もあるので、そういうマインドを浸透させたいと思いました。
── JFR花伝書の示す行動規範のもと、メンバーに「自ら考え、動いてもらう」ために、どんな育成プログラムを企画していますか。
野村: JFR花伝書の中に、JFRの課題解決に役立つナレッジを共有するためのケーススタディ集をつくっています。これは、私がつくるのではなく、JFRのさまざまな部門、職種、職位の人たちが集まって話し合いながらつくります。
仕事をする上では、実にさまざまな問題に直面するわけですが、その中には“答えのない問題”も少なくありません。こうしたビジネス課題に対して、JFRマインドに則ってどう解決するかをディスカッションしてまとめ、それを誰もが見ることができる形にしようとしているわけです。ちなみに、課題は「そもさん編」※、その回答を「せっぱ編」※としています。
※禅問答で使われる言葉。「そもさん」は問いかけの際、「せっぱ」は答える際のかけ声
一例を挙げると「前任者が失敗したあとに、DX戦略の担当になりました。引き継いで資料を読んでみたものの、1カ月たっても良いアイデアが出てきません。さて、どうするか」といった問い(そもさん)を立て、それについて、所属も職務も職位も異なるメンバーが集まって話し合い、答え(せっぱ)を考えていく──といった具合です。
ほかにも、JFRが持っている資産の新たな活用方法を、さまざまな店舗、部署、職位の人の目を通して考え、それにテクノロジーを絡ませることで、どんな新たな可能性が生まれ、顧客のニーズをとらえたビジネスにつながるのか──を掘り起こすワークショップを実施しています。
例えば、こんなお題について、みんなでディスカッションします。
「百貨店の屋上(資産)で、ファミリー層(顧客)のニーズがIoT(テクノロジー)によって満たされました。いったい、どんな取り組みをしたのでしょう?」

これは、前職で展開していた部門横断ワークショップをJFR向けに変えたものです。ちなみに前職では、「石の下(隠れている)のダンゴムシ(課題)を見つけて、それをどうやって救い出すか(どんな技術を使って解決するか)」をディスカッションする「ダンゴムシを探せ」というワークショップを行っていました。
JFRでは「JFRの持つ資産(アセット)」と「テクノロジー」、「顧客のニーズ」の組み合わせによる新たなビジネスのアイデアを考えることがゴールなので、少しアプローチを変えました。実際にやってみたところ、アイデアがとてもたくさん出てきて、参加した人たちの「いろいろな考え方を取り込んで形にしてみよう」という、とても強いエネルギーを感じました。
このようなワークを繰り返すことで、自分なりのアイデアを考えたり、立場が異なる人の意見を聞いたり、組織を超えて連携することの大切さを知ったり、諦めずに解決策を考えてやりぬいたり──といったことが身についてきます。これはビジネスをデザインしていく上での重要なポイントになるはずです。

うれしかったのは、一連の人材育成の取り組みを経営陣にプレゼンテーションして、「今度、実際にワークショップをやるんですよ」と話したところ、社長の好本がとても面白がって、「これはあの部署の○○さんや、この部署の○○さんにも体験させよう」と、自らさまざまな部署を巻き込んでくれたことでした。社外だけでなく社内にも、改革の重要性を常に発信し続けてくれるのは、とても心強いですね。
── JFR花伝書をベースとしたマインドのもとで考えたビジネスデザインを、実際に進めていく上でのガイドラインのようなものはあるのでしょうか。
野村氏: 企画・構想の段階から、検討や開発を進めていく上で注意すべき点をまとめた「システム開発のすゝめ」という教本をつくりました。ビジネスをデザインする上では、マクロ視点とミクロ視点の中で、構想から検討、開発、その後の運用フローを考えていくわけですが、その際にどこに気をつけて、どんなデザインを心がければいいのかがわかるようにしています。
そこでは、プロジェクトに関わる人たちとの関係性にも触れています。例えば、ビジネス課題の解決を考える際に、企画・構想をする人たちがIT部門を下に見て案件を雑に投げる──というのは、一般的によく聞く話です。こういう考え方をするのではなく、ビジネスとテクノロジーは対等であるということを意識して、フラットな関係のもとで顧客の課題を解決していこう、という話もしています。




── 実にさまざまな人材育成のためのプログラムを内製していますが、その意図は?
野村氏: おっしゃる通り、一部のスキル教育は外部のものを使いますが、それ以外の7〜8割は、ビジネススキルも含めて自分たちでつくっています。なぜ、自分たちでつくるのか──というと、自分たちの業態に合ったプログラムは、自分たちでつくらないと、「他人ごとの内容」になってしまうからです。
同じ百貨店やショッピングセンターというくくりの中でも、JFRだからこその文化や歴史があるわけで、課題解決の方法にしても、新しいビジネスを生み出すための方法にしても、JFRマインドに則ったやり方があるはずなんです。ですから、今、開発しているワークショップも、JFR花伝書の問答集も、自分たちの事例、自社のデータをつかって開発しています。
「ナレッジやマインドを自分たちの手でつくっていきたい」という声はJFR側からも挙がっていたので、とても進めやすかったですね。
どのような形でDXマインドをJFRに浸透させていくのか
── これまでお聞きした人材育成の取り組みは、具体的にどのような形で展開する計画ですか?
野村氏: JFRマインドのもと、「データアナリスト」と「デジタルデザイナー」というコア人材を育成する、というのが基本的な形です。最初はさまざまな部門から何人かを選んで学んでもらう予定で、「今いる部署に所属しながら学ぶ形」をとることに決めています。
なぜなら、改革人材だけを組織化すると、既存の組織との摩擦が起こる可能性があるからです。それを避けたかったのと、学んだことを持ち帰って、自分の部署で試してもらいたいという思いもありました。ただ、新しいことを学んで、これまでの部署でそれを生かそうとしても、孤立してしまう可能性がありますから、それを解消するために、学んだ人が集まるコミュニティを用意することにしました。コミュニティ内で試したことを共有したり、交流したりすることで、学んだことを定着させていこうとしています。
ゆくゆくは、学びたい人は誰でも学べるよう、プログラムの一部を全社に解放する予定です。こうすることで、さまざまな部署でのスキルの底上げを図るとともに、改革のためのコア人材の発掘にも役立てたいと思っています。

── どれくらいの期間で成果が出てくると思いますか? 変革の取り組みは時間がかかることが多く、経営陣が我慢しきれなくなることも少なくありません。
野村氏: ひと通り学んでから結果を出す、という形ではなく、学んだことをその都度、プロジェクトに生かしながら小さな成果を出していく──という形でのアウトプットを考えています。
経営者が成果を期待するのは当然のことなので、そこは小さい成果でも共有していく考えです。小さな成果が出ると、人は「もっとやろう」という気持ちになるものです。成果を見せて、経営陣が「そこはもっと強化したほうがいい」と思うのなら、「これだけの人とコストを投資すれば実現できます」と提案すればいいわけです。つまり、「人材が育つまで、しばらく待ってください」──というやり方はしないんです。
こうした小さなアウトプットを積み重ねながら、変革の土壌をつくり、プロセスをつくり、人を育て、同じマインドセットを持つ人たちが主要な部署にいる状態を、この先1〜2年で構築できれば、と思ってます。
DXの取り組みの先にあるJFRの姿とは
── 厳しいといわれているリテール業界ですが、このような取り組みを進めていくことで、JFRはどう変わっていくと思いますか
野村氏: JFRのことを知れば知るほど、「まだまだやれることがいくらでもある」とワクワクしてくるんです。グループ共通の価値を生かす取り組みはこれからですし、データもたくさんある。アプリユーザーも多いし、ライフタイムジャーニーの考え方に基づく取り組みも始まったばかりです。札幌、東京、大阪、名古屋、福岡といった大都市をカバーしているのも大きな強みになると思います。
百貨店やショッピングセンターのこうした取り組みの先にあるのが、どんな形のビジネスなのか──と考えるのが、実はとても楽しみなんです。
前職のANAは、もともとヘリコプターの会社で、それが市場のニーズに応えていく中で航空会社になりましたし、大丸や松坂屋は、元々は古着商や呉服屋で、長い年月を経て百貨店という形に進化しました。百貨店やショッピングセンターというビジネスモデルは一つの成果ですから、うまく生かしたいと思いますが、JFRが持つ有形無形の「資産」から新たな強みを導き出し、それをビジネスとしてうまくデザインすれば、新しいJFRの形が見えてくると思うのです。一緒にデザインしたいと思う方が増えてくるとうれしいですね。
例えば、来訪者データや行動データを掛け合わせると、「どんなお客さまが来店するとどんなことが起こるのか」「それは店舗にどんな流動を起こすのか」「その流動はどんな価値を生むのか」──といった、「購買データだけでは見えてこないさまざまな可能性の洞察」につながります。ここに手をつけるだけでも、新しい百貨店の形が見えてくるような気がしているのです。
こうした新たなビジネスモデルの先にあるのが「百貨店」という形にとどまるものなのかどうかすら、わからないですよね。そこも含めて、リテール業界には大きな可能性が広がっていると思うのです。