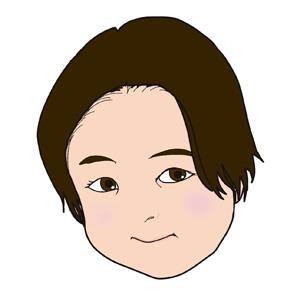現在、「デジタルトランスフォーメーション(DX)」へ取り組む多くの企業が、「マーケティング的思考」に関心を寄せている。テクノロジーを活用して、新たなビジネス価値を創出していくためには、「どのようなターゲットに対して(Who)」「どのような価値を提供するのか(What)」を常に考え続ける必要がある。こうした思考は、マーケティングの基本でもあるからだ。
AnityA(アニティア)は、2023年8月28日に「ITリーダーのDX戦略に『マーケティング』が必要な理由 改革に欠かせないビジネスセンスの育て方」と題したイベントを開催した。同イベントの前半では、LIXILの常務役員であり、Marketing部門のリーダーを務める安井卓氏と、マーケティング領域の人材育成サービスを提供する「グロースX」のCOOである山口義宏氏の両氏が、DXの文脈から見た「マーケティング」の重要性について講演を行った。
後半では、AnityAの代表取締役である中野仁氏が司会を務め、講演で触れられたいくつかのテーマを深く掘り下げるパネルディスカッションと、聴講者の質問に登壇者が回答するQAセッションが行われた。
本稿では、イベント後半の内容をダイジェストでレポートする。なお、イベント前半に行われた講演の内容は、別の記事でレポートしている。合わせて一読してほしい。

【登壇者】
・安井卓氏…LIXIL 常務役員 Marketing部門リーダー
・山口義宏氏…グロースX 取締役COO
・中野仁…AnityA 代表取締役(司会)
「プロモーション」は「マーケティング」の一要素に過ぎない
ディスカッションの冒頭、AnityAの中野氏は、今回のテーマに「マーケティング」を取り上げた理由について触れた。LIXIL安井氏の講演内容にも共通する問題意識として「“マーケティング”という言葉が、多くの企業や組織で“プロモーション(宣伝、販促)”の意味でとらえられている」ことに危機感を覚えているとする。
「安井氏の講演でも触れられたが、“マーケティング”は“企業活動全体”を指していて、プロモーションは、構成要素にすぎない。つまり、会社全体を理解する前提に立たなければ、マーケティングを考えることはできない。DXにおいても、組織の本質的な改革を考える場合には、マーケティングとして、“誰に(Who)”“どんな価値を(What)”提供すべきかを考える必要がある。それを元にTo-Be(ありたい姿)が立てられていなければ、ゴールがない状態となり、改善も進められない」(中野氏)
安井氏は、講演の中で「マーケティング=企業活動そのもの」であることを強調していた。
「マーケティングと言ってしまうと、“プロモーションをやって売れるようにすればいい”と考えられてしまうケースが多いが、実際の“売れる仕組み”はそこにない。企業としての事業の組み立て方やビジネスモデルから考えた場合、ターゲットとなる顧客にミートしない商品を、プロモーションの力に頼って売っても、意味がないのではないか。企業として、顧客に対しどのような価値を届けるのかを、しっかり理解して取り組んでいくことの重要性が増しているということを言いたかった」(安井氏)

山口氏は、現在、多くの企業で「マーケティング」が「販促、宣伝」といった限定的な意味合いで受け取られている理由のひとつに「組織名称の問題」があるのではないかと指摘する。以前、大手電機メーカーの子会社で戦略コンサルティングを手がけていた同氏は「日本のメーカーでは、販売を統括する子会社に“○○マーケティング”と社名を付けることが流行した時期があり、そういった組織名称が現在の認識につながっているのではないか」とした。
「商品企画の話をしているのに、会議の場で“マーケティング”という言葉を出すと、相手には、広告や販促のような“後工程”の話をしていると受け取られることがあった。そのため、ある時期から“マーケティング”と言う際には、どの範囲で話しているのかを意識するようになった。恐らく、社内で“マーケティング”について話す際には、共通の認識と言語を持つことが必要になっているのではないかと思う」(山口氏)
中野氏は、「部署名によって、対象への認識が分断してしまう問題は、“IT部門”“情報システム部門”といった形で、ITシステムへの取り組みにおいても、同じ構造があるように思う」と述べた。
社内向け施策にも有用な「マーケティング」的思考
続いて中野氏は、安井氏が講演の中で紹介した、LIXILにおける個々の施策について「展開にあたって、その施策を“何のためにやるのか”を、社内できちんと伝えてきたという印象を受ける。その点は、特に意識していたか」と質問した。安井氏は「相手に伝えることは意識していたが、当初はそれが“マーケティング”的なものだとは意識していなかった」と振り返る。
「LIXILへ入社したとき、いろんな人と話をして、声を聞くようにしていた。個々の施策については、とりあえずやってみて、ユーザーの反応を見たり、グチを聞いたりしながら課題を見つけ、その解決策を探して実行するということを繰り返した。“何のためにやるのか”を考えず、解決策だけを出してしまうと、リアルな課題解決につながらない」(安井氏)
例えば、コミュニケーションツール「Meta Workplace」の全社導入にあたっては、ユーザーの反応を見ながら、複数の競合サービスを比較し、LIXILグループに最も適切と思えるものを選択したという。
「前職では、コミュニケーションツールとしてSlackを利用していたが、5万人規模の組織にチャットベースのツールは合わない。複数のツールを備えたSNSベースのもののほうがふさわしい。そういうことを考えながら、ベストではないにしても、ベターな解決策を提供していった」(安井氏)
こうした安井氏の取り組みは、「まさに“誰に?”“どんな価値を提供する?”というマーケティングの基本に則したアプローチと言える」と中野氏は指摘した。
「こうした取り組みを進める時には、どうしても具体的な施策、つまり“どのように?(How)”の部分から積み上げがちになる。WhoやWhatをベースに、仮説を立てて議論していかないと、施策とコストばかりが積み上がって、結局何がしたかったのかが分からなくなる」(中野氏)
「仮説検証は大事だけれども、それをやるためには“実験”を積み重ねるしかない。まずは、小さくやる。それに対して、どういう反応があるかを、その都度観察する。そうやって打席数を増やすことで、成功の確率が上がっていく。その繰り返しだと思う」(安井氏)
「小さな実験を繰り返す」ことについて、山口氏は「プロモーション」も同じ構造だと指摘した。
「最初は小さな成功体験を作り、“だれかに価値が評価されている”と数字を含めた手応えのある状態にしてから、投資額を増やしてリーチを広げていくのが成功への近道。この手順を踏まないと、大きな失敗を招く」(山口氏)

まずは「How」ではなく「Who」と「What」から考える
「誰に(Who)」「どんな価値を提供するのか(What)」を、掘り下げることの重要性について、中野氏は、山口氏が講演の中で「マーケティング人材育成ビジネスを提供する中で、DX文脈での需要があることに気づいた」と話した点を取り上げた。
「マーケティング関連部門をターゲットにサービス提供を行う中で、一度、サービスを受けた企業が、後に部門横断で使ってくれるケースが多いことに気がついた。その理由をヒアリングしたところ、発注主体がDX推進部門や人材育成部門になっていて、いわゆる“DX”の文脈でのニーズがあることに気づいた」(山口氏)
これについて、中野氏は「サービスを提供する側が“誰に”を深く掘り下げた結果が、新たな顧客獲得につながった例だろう」と指摘した。
「事業の中で、“誰に”“どんな価値を”といった部分の掘り下げを、調査会社や一部の社員だけがやっていて良いのかという問題意識がある。特定の誰かがやるのではなく、社内で顧客のことを知りたいと思った人が、思いついたらすぐにやる。そのレベルまでルーチン化することが必要だと思う」(山口氏)
安井氏は、こうした構造はマーケティングに限らず、IT領域でも問題になることがあると指摘した。
「ITシステムの導入において、実際のユーザーではなく、企画部隊が“こういうことをやりたい”と企画を立ち上げるケースがある。この場合、企画者と実際のユーザーが別であるために、最終的にできあがるものがミスマッチになってしまうことが多い。これは、企画部隊が悪いわけではない。企画部隊は“業務効率化”の視点からシステムを考えるし、ユーザーは現場で“使う”視点でシステムを評価する。どちらかの視点に偏りすぎてはダメで、バランスが大切」(安井氏)
こうした「視点の違い」は企画者とユーザーとの間だけでなく、「決裁者」との間にもあると山口氏は付け加えた。
「決裁者の視点では、ROIが重要になる。エンドユーザーの視点で、UI/UXが大切だというのが分かっていたとしても、そうした部分は決裁者に刺さらない。結果として、UI/UXの洗練されていないシステムが作られ、ユーザーは苦痛を感じながらも、使わざるを得なくなる」(山口氏)
「そうした視点の違いを吸収するためにも、マーケティング的思考がカギになるのではないか。ユーザー、企画者、決裁者といった特定の相手のみを想定するのではなく、その場に応じて、どんなターゲットに、どういうアプローチで価値を提供できるかを考えて訴求する。単純化すれば“声を聞く相手と数を増やすべき”ということではないか」(安井氏)
「How」は概要を全員が理解して専門家が実行する
山口氏は講演の中で、マーケティングの「施策」が、特にネット時代において、細分化、専門化する傾向にあり、特定の人や組織が、全領域で最新状況にキャッチアップし続けることが、事実上不可能になっていると指摘した。その前提で、施策については、まず「誰に(Who)、どんな価値(What)を提供するか」という部分について共通認識を持った上で、実際の「施策(How)」は、すべての人が概要のみを理解しておき、実行は社内外のふさわしい専門家が行うスタイルが現実的だとした。
中野氏は、この内容を受け「IT領域においても、まったく同じことが当てはまる」とした。
「ITにおいても、セキュリティやインフラなどの領域で、顕著に細分化、専門化が進んでいる。解決策を考える上で、各領域の概要は、インデックスとして頭に入れておく必要があるが、概要を把握する以前に、各施策の詳細を深掘りしてしまいがちな傾向がある。また、概要の知識を効率良く身につけるのが難しいという点でも、マーケティング領域と同じ課題があるように思う」(中野氏)

この指摘に対し、山口氏は「ベンダーやコンサルタントがビジネスとしてお金を引き出しやすいところと、顧客のビジネスにとって本当に大事なところが、若干ずれているという点で、問題の構造は似ているかもしれない」とした。
安井氏は、特に日本企業において「ITベンダーやコンサルタントに依存しすぎる」傾向があることが問題の根底にあるのではないかと指摘する。
「専門家としてのベンダーやコンサルタントに相談すること自体は悪くないが、責任の所在も含めて“丸投げ”してしまう傾向があるのは問題。知識やノウハウを借りながら、自分たちでもできるようになっていこうとする姿勢が必要なのではないか。それは、ビジネスをやっていく上で、決して難しいことではない」(安井氏)
中野氏は「外部に任せて良いところと、任せてはダメなところがあるという意識が不可欠。マーケティングやDXにおいては、各施策の概要の把握と、“Who”や“What”については、自分たちでやらなければいけないところ。これらを社外に握らせてしまうのは、自殺行為に等しい」と意見を述べた。
「思うに、顧客を知り、“Who”“What”を考えるというのは、仕事として一番“面白いところ”であるはず。自分たちで考え、実践して、失敗しても改善することを繰り返すべき」(安井氏)
「顧客を知るための方法は、直接お客さんに会ってインタビューすることだけではない。例えば、ITシステムの導入であれば、何らかの施策を打ったら、“どのくらい使われているか”といったフィードバックが、必ずデータとして残されている。それを可視化して吟味することで、施策がうまくいっているか、そうでないかが分かる。施策のフィードバックから、学んで解釈する。その習慣ができているチームは、とても強い。ある意味で、組織内にそうしたチームを作っていくことが、状態面でのゴールであるように思う」(山口氏)
「施策を実施する際には、前もって何らかの仮説を立てるはずだが、“仮説は当たらない”という前提で、データとして得られたフィードバックをもとに、新たな仮説を立てるというループを回すことが大事。施策の軌道修正は当たり前ととらえ、スタート時には小さく始め、一回の失敗で全体が破綻しないような枠組みを構築していく方法を考えるのが、本来の“企画推進”の役割であり、それはとてもクリエイティブな仕事だと思う」(中野氏)
DXや組織改革に取り組む企業に共通する「問題」の打開策を考える
イベントの最後には、聴講者から寄せられた質問に答えるQ&Aセッションが設けられた。以下では、その内容を抜粋して紹介する。
質問: ITツールを導入しても、組織文化が変わらなければ効果が出ないと感じている。LIXILでも、ツールの導入と合わせて組織文化の変革に取り組んだと思うが、その際の苦労話を聞きたい。
「時間をかけて培われてきた文化は、簡単には変わらない。LIXILの場合は“文化”を変えるのではなく“行動”を変えようとしてきた。現場だけでなく、トップへのアプローチも並行して行うことで、現場が変わらざるを得なくなる状況を作るのも、ひとつの方法だ。例えば、DX施策としてノーコードツール(Google AppSheet)を全社に普及させる際には、最初に経営陣にアプリを作らせた。Meta Workspaceの導入時も同様で、週報をWorkspaceで提出するなど、ツールを使わざるを得なくなるようなルールを作った。一度使い始めれば、現場もトップも価値を理解し始めて、徐々に行動が変わっていく。1カ月、1年といった短期間で成果を判断するのではなく、“3年間かけて変えていく”くらいの意識が必要だと思う」(安井氏)

質問: 安井氏から「DXは最終的に企業の利益に貢献しなければ意味がない」という話があった。しかし、ITツールの新規導入は、短期的な利益につながりにくく、経営陣からの承諾が得づらいと感じている。
「 “そのツールを入れて、どれくらい利益が上がるのか”と聞かれても、直接の数値を示すことは難しい。しかし、従業員体験(EX)が改善されると、顧客体験(CX)が上がり、CXが上がれば最終的に利益につながるということを経営陣が理解できていれば、ロジック上はつなげることができる。あとは、担当者の情熱。“私は、このツールを入れることでEXを上げたい”“このツールでコミュニケーションを変えたい”という熱意が伝われば、理解は得られることが多いと思う。導入の理由が“コンサルタントが言ったから”では伝わらない」(安井氏)
「まず小規模に使い、成果を作るという体験を時系列で積み重ねていくことが大事。他社の事例を参考にするのではなく、自社でパフォーマンスが出たものを、改善しながら積み上げていくことが次につながる」(山口氏)
質問: DXの初期段階では、デジタルツールの導入が不可欠だと思うが、社内にそうしたツールを使って仕事をすることを嫌がる人がいる。どのような対策が考えられるか。
「そういう人はたしかにいて、その人が今現在の利益に貢献しているような場合は特に難しい。その場合、その人の周囲にいる人たちが、ツールを使っている状態にすることがポイントになる。人数が増えることで、どこかでキャズムを超える。たとえば、組織全体で、コミュニケーションの主役がメールからチャットに移れば、仕事をしていく上で、チャットを嫌っている人も使わざるを得なくなる。そうした状況に持って行くのがいいと思う。あと、社内でエンドユーザー向けの仕組みを導入する際にはマニュアルを作るのが一般的だと思うが、できればマニュアルを見なくても使えるような、UI/UXの良いものにすることも大切。周囲の人がみんな使っていて、なおかつエクスペリエンスが良ければ、大抵の場合は使ってくれるようになる」(安井氏)

「どんなに導入を工夫して、ツールのエクスペリエンスを改善したとしても“絶対に使わない”という人は、大規模な組織であれば一定数存在する。そういう人に対しては、人事管理的に“ローパフォーマー”であるという評価をつけるという手段もあり得ると思う。経営の視点で見れば、ツールの導入は“従業員向けの投資”であって、従業員を甘やかすことが目的ではない。その意識はあってしかるべき」(中野氏)
質問: 自分はIT部門の立場から、事業会社のDX支援をしているが、顧客理解、課題把握に限界を感じている。組織横断でDXを支援する際に注意すべきことがあれば聞きたい。
「解決すべき課題の立て方に帰結するのではないか。リソースに限界があって、全部に手が回らないのであれば、全体の利益に一番貢献できる部分を見つけて、そこからアプローチするという考え方もある。たとえば、課題が組織のサイロ化であれば、各部門で共通項を見つけて一元化することを最初の目標にするといったことは可能だろう」(安井氏)
「この質問のような状況は、多くの会社で共通して起こっている。IT部門が、全事業の全顧客を把握しようにも限界がある。そもそも、事業部門側でも、すべてを把握できていないことがある。そうした状況で“広く、浅く”やろうとすると失敗することが多いので、まずは短期間で成果が望めそうなところを見つけ、そこに集中して成功事例を作った上で、周囲を巻き込みながら、やり方を横展開していくのが現実的だと思う」(山口氏)
「LIXILでやったことのひとつは、IT部門が“あきらめる”ということ。事業部門からの要望は多いけれども、IT部門はリソースが足りておらず、そのすべてを実現することはできないと宣言した。望むツールをIT部門で作ることはできないが、使いやすいツールを入れて、トレーニングもするので、自分たちでやってほしいとお願いして、その仕組みを作った。“IT部門ですべてやることをあきらめる”というのも、限界を超えるための方法のひとつ」(安井氏)
悩み多きDX推進のリーダーへ「伝えたいこと」
Q&Aセッションの後、安井氏、山口氏は、それぞれに聴講者に対してメッセージを述べて、イベントを締めくくった。

「今日のセッションを聞いて“LIXILではすごいことができている”と思った人がいるかもしれないが、実際には、やりたいと思って、できていないことのほうが圧倒的に多い。DXや組織変革がうまくいっていないと感じている担当者、会社は決して少なくない。みんな、同じような問題を抱えているのが現実だと思う。みんなで知恵を出し合いながら、一緒に問題解決をしていきましょう」(安井氏)
「世の中、一発で何かがうまくいくことはほとんどない。成果に向けて、施策を積み重ねていくことが大事。今日のセッションで私が伝えたかったのは、ひとつ一つの施策を実施する際に“誰の(Who)”“どんなニーズを満たす(What)”ための施策であるかを強く意識するということ。そして、顧客のニーズを知る方法は、お客さんに直接聞きに行くだけではないということ。それが難しければ、社内で顧客に一番接している人に聞きに行くという方法もある。まずは1カ月、そうしたアクションを続けてみることで、何らかの変化があるはずです」(山口氏)
ITリーダーのDX戦略に「マーケティング」が必要な理由 改革に欠かせないビジネスセンスの育て方