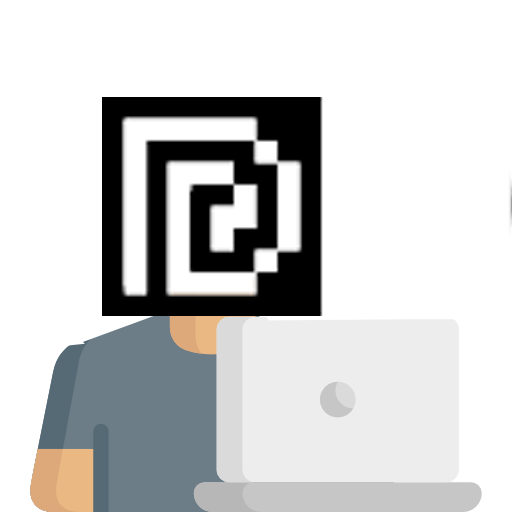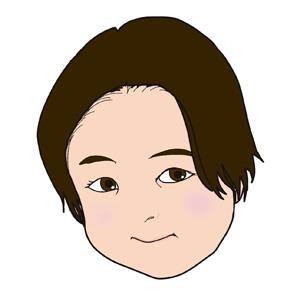※本記事は、DX時代にあった新しい企業システムのあり方を考えるコミュニティ「BJCC(Box Japan Cloud Connections)」のコラムとして2020年11月18日に掲載された記事を転載したものです。
新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言によって、企業が働き方を変えざるを得ない状況に追い込まれた2020年。本特集のインタビューを行う中、企業のリーダーたちが口を揃えるのが「企業の二極分化が加速している」ということでした。
今回、話をお聞きした、ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ(以下、ケンブリッジ) バイスプレジデントの白川克さんも、そう話す一人です。
なぜ、コロナ禍が企業の二極分化を加速させるのか、成長企業とそうでない企業を分かつものは何なのか──。
ITコンサルタントとして長年、企業のIT変革を支援してきた白川氏に、企業の二極分化が加速している背景とそれを引き起こしている要因、そしてコロナ禍でも成長し続ける企業になるための方法についてお聞きしました。

コロナ禍で明確化した「企業の二極分化」とは
── 新型コロナウイルスの感染拡大を経験したことで、人々の働き方は大きく変わりました。ITコンサルタントとして、このコロナ禍をどのように捉えていますか。
白川克: コロナ禍が、「企業の二極分化」を加速させている印象を受けますね。
緊急事態宣言が発令されたことから、企業は半ば強制的に社員の働き方を変えざるを得なくなりました。企業は、できるだけ社員を出社させずに仕事を回せるようにしなければならなくなったわけです。
こうした事態が起こった今、企業の対応をみていくと、コロナ禍以前から「ITをうまく利用して会社を変える」という意気込みで業務改革に取り組んできた企業がある一方で、「これまでのやり方を変えたくない」「新しいことを覚えるのは面倒」と、業務改革に対して消極的だった企業も少なくありません。私はコロナ禍に直面して、こうした企業の二極分化がさらに加速していると感じています。
── 業務改革に積極的な企業と、現状維持に固執する企業が二極化しているということですね。それを分かつものは何だとお考えですか。
白川克: これは、私たちが企業のデジタルトランスフォーメーション(以下、DX)を支援する中でも感じていることですが、社員が「やらされ仕事をしている企業」と「オーナーシップを持って仕事をしている企業」の差が顕著になっているのではないか──と思うのです。
この「オーナーシップを持って仕事をする」というのは、「仕事を自分ごととしてとらえ、自ら考え、自分の責任において完遂すること」を意味しています。
── 社員が「やらされ仕事をしている企業」と「オーナーシップを持って仕事をしている企業」の違いはどのようなものなのでしょうか。
白川克: 例えば、当社にも「DXに取り組みたい」という企業からの相談が増えていますが、話を伺ってみると、その内容はふわっとした抽象的ものであることが多く、「DXで何を実現したいのか」が明確になっていないケースも少なくありません。このような環境下で「DXをやれ」と言われても、現場は何をしたらいいのか分からないですよね。
その結果、IoT(Internet of Things)やAI(人工知能)など、新技術の導入を検討し、PoC(実証実験)を繰り返しては尻すぼみになっている。こんなことになってしまうのは、DXに携わる現場の社員が、上から「DXをやれ」と言われたから「何か新しいことをやっている」だけで、「“自分ごと”としてDXに向き合っていないこと」が原因だと感じます。
一方、現場の社員が、「自社の課題を解決するために『当事者意識を持って』DXに取り組んでいる企業」は、意思決定や作業にスピード感があるんですよね。社員にこの気概があるかどうかで、企業の将来は大きく変わってくると考えています。
「オーナーシップを持って仕事をする人材」はどうやったら育つのか
── 社員が「オーナーシップを持って仕事ができるかどうか」は、企業の「組織のあり方」とも関係してくるのではないでしょうか。
白川克: そうですね。企業の「組織に対する考え方」とも深くかかわってくる話だと思います。
「やらされ仕事」、いいかえれば「とにかく上の指示に従う」という仕事の仕方は、「均質なものを大量に作ることで稼げていた“昭和”の時代」には成立していたので、企業によっては“令和”になった今だと、企業文化を変えていく話になるのかもしれません。
企業が文化や働き方を変えるカギになるのは、トップダウンの指示というより、現場に近いところにいるミドル層の「自社の課題を理解した上でのふるまい」だと私たちケンブリッジは考えているんです。いわゆる「ミドルアップダウン」とよばれる手法で、この場合はミドル層が部下にオーナーシップを持った仕事をするよう働きかけ、その効果をトップに見せるというやり方です。
なぜ、そのように考えるかというと、理由は「日本企業の経営層がミッションやビジョンに基づく、真の意味での経営戦略」を立てることに慣れていないと思うからです。
一般的な話として聞いていただきたいのですが、企業が経営戦略を立てるときには、トップが「企業としてどうありたいか」を考えた上で方針を示し、ミドル層以下がその方針に従って「考えて」実行するのが前提です。
しかし、日本では「企業のトップが明確なミッションやビジョンを示せていない」ケースが少なくないんです。仮にあったとしても、「何百億円の売上を目指す」という数値目標になっていたり、単なるスローガンで終わっている企業も散見されます。そんな状態では、トップダウンで企業の文化を変えていくのは難しいですよね。
一方、私たちが、「“ファシリテーションの手法”を使って企業の変革を支援する」活動を続ける中で実感したのが、「実は自社の課題を正しく認識し、そこに最も高い危機感を抱いているのは、『現場に近いミドル層』なのではないか」ということなんです。
そこからたどり着いた企業改革の手法が「組織の“実のキーマン”であるミドル層に、部門を超えたフラットな場でのディスカッションを通じて『会社をより良くするためのコンセプトやゴールを導き出してもらう』というアプローチ」でした。
そんなアプローチに基づくミドル層の行動が、「オーナーシップを持って仕事をする社員を育てる」ための、よい方法である──という結論に至ったのです。
── 社員にオーナーシップを持たせることと、ミドルアップダウンのアプローチは、どのような関係性があるのでしょうか。
白川克: 日本のビジネスパーソンは自社愛があり、「会社をより良くしたい」という気持ちを持っている人がほとんどです。ですから、その気持ちを最大限に生かし、結果につなげるためには、社員に「外圧で仕事をさせる」のではなく「仕事を“自分ごと”としてとらえてもらい、誇りと責任を持って仕事ができるようにすること」が重要なのです。
具体的には、企業の中核を担うミドル層から課題解決のためのアイデアを集ります。そして「この取り組みは会社全体により良い変化をもたらすのか」「長期的な利益と価値の向上につながるのか」を徹底的に議論する。その上で、「責任を完遂できるであろう範囲」で部下に仕事を任せ、オーナーシップを発揮させてプロジェクトをやり遂げてもらうのです。
ここで大事なのは、入社間もない社員であっても、彼らが負える範囲で責任のある仕事を任せることです。そして、プロジェクトでの小さな仕事で成功体験を積み重ねながら、徐々にプロジェクト全体を“自分ごと”にしていってもらうわけです。プロジェクトのメンバーが、このようなマインドで仕事を続けることが、次第に全社的な改革につながり、あとから振り返ったときに「結果的にDXに取り組んでいたんだ」という状態になるのが理想だと考えます。
── たしかに日本企業のミドル層は、自社の課題や澱(おり)を熟知している人が多いですが、所属部門の力学や組織の論理に屈して問題点を指摘できず、ネガティブなことをやり過ごしてしまうケースも少なくありません。その結果、「言われたことさえやっておけば、マイナス評価にはならない」と、改革に消極的になってしまうのではないでしょうか。
白川克: たしかに、そういうこともあるかもしれません。でも、情報システム部門で働いている人にとっては、「言われたバグを修正するという仕事」よりも、「ITツールを駆使してコミュニケーション設計し、社員の利便性を向上させる仕事」の方がやりがいがありますし、楽しいですよね?
考えてみてください。上司から「Boxを使えるようにしておいて」と言われて設定するだけの仕事と、従業員同士のコラボレーションをITで支援するにはどうしたらよいか、を考える仕事では、取り組む際のモチベーションが違うと思いませんか? 前者は「やらされ仕事」、後者は「自ら考え、責任を持ってやる仕事」、すなわち「オーナーシップを持ってする仕事」ですよね。
後者のアプローチで課題を解決するには、例えば、BoxやZoom、Slackを組み合わせて最適なコミュニケーションやコラボレーション環境を考え、同時に情報漏えいのリスクを分析してセキュリティポリシーを策定する──という手法になるかもしれない。これを実現するには、各ソリューションに対する知識や調査も必要ですし、他部門の担当者との交渉も不可欠ですから、オーナーシップを持ってあたらなければ、到底不可能です。
さらに、コロナ禍で社員の働き方が大きく変わった今、情報システム部門の責任範囲は急拡大しています。
リモートワークが増えているコロナ禍の職場では、コンテンツの共有やコラボレーションのための仕組みとしてITが不可欠ですから、こうした社内コミュニケーションを円滑にするためのシステム設計は、情報システム部門が関与しないことには成立しません。この分野は、これまで人事部門や総務部門が主導権を握っていましたが、今や情報システム部門の協力なしには導入も運用も難しいでしょう。全てがITの上に載るのがウィズコロナ時代ですから。
情報システム部門にとってコロナ禍の今は、企業の働き方改革に大きく貢献できるチャンスです。その時にメンバーそれぞれがオーナーシップを持って自分の任務に当たり、その結果、リモート環境下での働き方がよりよくなっていけば、組織全体のモチベーションが上がっていきます。プロジェクトにはそうしたマインドが必要なのです。
人を成長させるのは「当事者意識」と「責任ある仕事」
── 変革プロジェクトを推進する上で留意すべきポイントとは何でしょうか。
白川克: まずは「現場の状況」と「解決策になりうるソリューション」を知ることですね。ITシステムであれば、現場の課題は何かを直接、その場に行ってヒアリングし、現場にとって最適な解決策は何かを考えることです。その際、ミドル層は常に、部分最適に陥ることなく、「会社全体にとってどうなのか」という視点を併せ持つことも重要です。
今やITを取り巻く環境は急激に変化しています。例えばクラウドが普及する以前は、ITシステムを構築する製品は、それほど選択の幅がありませんでした。ですから、「この用途にはこの製品」というように、ある程度選択肢が決まっており、情報システム部門はその範囲内で作業をすればよかったのです。
しかし、クラウド全盛の現在は、製品やサービスの数が増えていますし、現場のニーズも多様化しています。よって、現場のニーズも、すごいスピードで変化しているITも知らずに「ITをテコに会社を変えよう」と意気込んでもうまくいきません。
もう1つは、部署を横断するプロジェクトに「所属部門の利害関係を持ち込まない」というルールを設けることです。そこに組織や部門の力学を持ち込むと、プロジェクトの“軸”がブレてしまいますし、メンバーが、「プロジェクトを成功させるために“自分”が何をすべきか」に集中することができなくなってしまいます。
部署を横断するプロジェクトは、複数部門に関係するさまざまな業務が幾重にも重なるカオスな状態です。プロジェクトの中で特定のタスクを担ったら、自分の所属部門に関係なく全社としての利益を考え、責任を持ってタスクに取り組むことが重要です。このようなプロジェクトを通じてオーナーシップを持つことを学んでいくのが、社員が成長する過程でとても大切なことだと思うのです。
── 白川さんが担当したプロジェクトの中で、特に社員の方々の成長を実感できた案件はありますか。
白川克: 私の著書、「リーダーが育つ 変革プロジェクトの教科書」(日経BP社刊)でも紹介した、住友生命保険相互会社の「青空プロジェクト(通称)( https://www.ctp.co.jp/case_study/case110/ )」は、とても印象に残っています。全部で数百人が関わる大きなプロジェクトだったのですが、開始当初はいちばん下っ端だった若手メンバーが、3年後にはプロジェクト全体のリーダーになったのです。
そのプロジェクトは、変革人材を次々と輩出することで社内でも注目される存在になり、プロジェクトメンバーが上からどんどん社内の要職に引き抜かれていったことから、玉突きで上がった──という側面もあるのですが、それにしても、彼の成長は目を見張るものがありました。上司が彼のオーナーシップを徐々に広げていったところ、どんどん自分で新しいアイデアを提案するようになったんですね。
このプロジェクトで、私たちがファシリテーターとして留意したのは、メンバー全員に「自分がプロジェクトを進めることに貢献している」という実感を持ってもらうことでした。「自分の提案やアイデアが、プロジェクトを前に進めている」ことをメンバーに確信させることで、オーナーシップを持ってプロジェクトにハマっていくように仕向けたのです。結果を実感できれば、人はさらに伸びる好例でした。
「自分で仕事を見つけ、やり遂げること」がオーナーシップマインドを育む
── オーナーシップを持った仕事をするためには、経営者の視点が必要なのでしょうか。
白川克: たしかに経営者目線でビジネス鳥瞰することは重要ですが、私は全ての社員が経営者目線を持つ必要はないと考えています。人にはそれぞれ得意/不得意があるように、経営者目線で全体を見られる人もいれば、細かい改善ポイントを見つけるのが得意な人もいますよね。
大事なのはプロジェクトのリーダーが、メンバーの特性を把握すること。そして、「誰にどの役割を任せれば、チームとして最大限のパフォーマンスが発揮できるのか」「それがプロジェクト全体にどのようなインパクトを与えるか」を考えることです。
だれでも「仕事をするからには楽しくやりたい」と考えますよね。ですからリーダーは、メンバー全員が「自分は、このプロジェクトに欠かせない存在なんだ」と、必要とされている感覚を持てるような環境を作り出すことが重要です。
── 社員がオーナーシップを持って仕事をするには、どのようなマインドが必要なのでしょうか。
白川克: 最近は、働き方改革の考え方が企業に浸透してきたことから、「残業は悪」であり、時間内に効率よく作業することが「良し」とされる傾向があります。義務としての仕事を効率的に遂行するのはよいことだと思いますが、若いうちは「スカンクワーク」(※注 本来やるべき業務以外の自主的活動)をぜひやってほしいと思うんです。上司から指示された仕事ではないけれど、自分が「会社のためになる」「社会のためになる」と思ったことにチャレンジすることはとても重要だと思います。
もちろん、上司に応援してもらえればベストですが、誰から指示されたものでもなく、自分で仕事を見つけてそれをやり遂げることこそが、究極の「オーナーシップ仕事」です。特に、管理職ではないメンバークラスの社員にとっては「会社のために何をすべきか」を考える訓練にもなるはずです。
── お話を伺っていると「仕事を楽しむこと」が何より重要だと実感します。
白川克: 当社の行動指針の一つに「Have Fun!」という言葉があるのですが、まさにこれに尽きると思います。
“自分ごと”としてオーナーシップを持って、自分の仕事を楽しむこと──。そうすれば、「誰のために、何を改善するか」を自分で考える力が付きます。自ら考え、責任を持って仕事をする人が増えれば自然と改革が進み、それが会社全体の変化につながる。DXって、本当はそういうものだと思うんですよね。現在、それが企業の成長に必要なことだと思います。